目次
酒さとは

酒さ(しゅさ)は、主に顔面に慢性的な赤みやほてり、小さなブツブツ(丘疹・膿疱)などが生じる慢性炎症性皮膚疾患です。
頬、鼻、額、あごといった部位に出やすく、毛細血管が拡張して赤みが目立つようになります。
お酒をよく飲む人にみられると考えられていたため「酒さ」と呼ばれますが、実際には飲酒と関係なく発症することも多く、体質や皮膚のバリア機能の低下、外的刺激などが関係しています。
30代以降の成人、特に40~60代の女性に多く見られる傾向がありますが、近年では20代の女性でも見られ、また男性でも発症することがあります。
特に敏感肌で、赤くなりやすい、熱を持ちやすいといった特徴を持つ方が発症しやすいとされています。
また、酒さは他の疾患と見分けがつきにくいことも多く、長期間、別の皮膚疾患と思い、過ごしている方も少なくありません。
進行性の皮膚病であるため、早期に適切な診断と治療を受けることで症状をコントロールし、悪化を防ぐことが重要です。
見た目の変化による精神的な負担も大きいため、当院までお早めにご相談ください。
酒さの症状
酒さで見られる主な症状は、以下の通りです。
- ほてり
- 赤ら顔
- ブツブツ(丘疹)
- 膿をもったできもの(膿疱)
- 鼻瘤
- 眼の充血や異物感
ほてり、赤ら顔
酒さの症状は、段階的に進行することが多く、初期には顔面のほてりや一時的な赤ら顔として始まります。
時間が経つにつれて赤みが持続するようになり、皮膚表面に毛細血管の拡張がみられるようになります(紅斑型)。
この段階では、日差しや温度差、辛い食べ物、アルコールなどが引き金となって赤みや火照りが悪化することがあります。
ブツブツ(丘疹)、膿をもったできもの(膿疱)
中等度から重度になると、赤みの中に小さなブツブツ(丘疹)や膿をもったできもの(膿疱)が現れるようになります。
これは一見ニキビに似ているため、「大人ニキビ」と思い込んで市販薬を使ってしまう方もいますが、ニキビとは発症の仕組みも治療法も異なり、誤った対応によって悪化することもあるため注意が必要です。
鼻瘤
さらに進行すると、皮膚の厚みが増したり、特に鼻がごつごつと変形してくる「鼻瘤(びりゅう)」と呼ばれる状態に至ったりすることもあります。
この状態は、主に中高年の男性に多くみられますが、日本人ではあまり多くないとされています。
眼の充血や異物感
酒さは眼にも影響を及ぼすことがあり、「眼型酒さ」と呼ばれる眼の充血や異物感、かゆみ、乾燥、涙目、まぶしさなどの症状が出ることもあります。
酒さの原因
酒さの明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、外部環境、皮膚のバリア機能の低下や免疫異常、血管の過剰反応、皮膚常在菌の関与、遺伝的素因、など、複数の要因が絡み合って発症すると考えられています。
血管の拡張
まず、酒さにおいて最も特徴的なのが「毛細血管の拡張」です。
これを悪化させる因子としては、以下のものがあります。
- 寒暖がはっきりした環境(特に寒冷曝露)
- 熱い飲み物
- アルコール
- カフェイン
- 香辛料の効いた食べ物の摂取
- 紫外線への曝露
- 喫煙
- 興奮すること
- 過度の運動 など
これらが要因となり、顔の赤みやほてりを引き起こします。
ホルモンバランスや自律神経の乱れ、ストレス
このほか、ホルモンバランスや自律神経の乱れ、ストレスなども症状の誘因となると考えられ、さらに毛包に常在するダニの一種「デモデックス(毛包虫)」も酒さの悪化の原因に挙げられています。
他の疾患
酒さの方は、炎症性腸疾患やリウマチなどの自己免疫疾患、パーキンソン病などを罹患していることが多いという報告もあります。
腹部症状、関節痛、神経症状などを伴う場合は、外的要因と全身性の疾患など内的要因を見ていく必要があると言われています。
酒さの治療
酒さの治療にあたっては、まず、似た症状を呈する別の疾患と区別することが重要です。他疾患としては、ニキビ、接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、花粉症皮膚炎、膠原病などがあります。
検査ではダーモスコピーによる皮膚の観察などで、見極めていきます。
ただし、これらの疾患は酒さと合併して発症していることも少なくなく、酒さと同時並行で治療していくことが重要です。
酒さ(しゅさ)の薬物治療は、症状の型(紅斑・毛細血管拡張、丘疹・膿疱など)や重症度、患者さまの肌質・体質に応じて慎重に選択されます。
ロゼックスゲル(メトロニダゾール)
使用する薬剤としては、「ロゼックスゲル(メトロニダゾール)」が赤ら顔の治療に有効です。
これは2022年5月に保険適用での使用が可能となりました。
ニキビダニや寄生虫、嫌気性菌に対する抗菌作用があり、抗炎症作用や免疫抑制作用などもあるため、酒さの改善が期待できます。
炎症を和らげ、毛包虫(デモデックス)の関与が疑われる場合にも有効です。
塗布後数時間で赤みを軽減する即効性がありますが、反動性の潮紅が起こることがあるため、少量から慎重に使う必要があります。
イオウ・カンフルローション
イオウ・カンフルローションも保険適用となっています。
殺菌・角質軟化・収れん作用を持ち、比較的軽症の症例や脂漏性変化を伴う酒さに対して用いられますが、刺激性があるため使用部位や頻度に注意が必要です。
抗菌薬
内服薬としては、ミノマイシン(ミノサイクリン)やビブラマイシン(ドキシサイクリン)などのテトラサイクリン系抗菌薬が中等症以上で用いられ、主に抗炎症作用を目的に数週間~数ヶ月投与されます。
テトラサイクリン系抗菌薬が使えない方はルリッド(マクロライド系抗生物質)を使うことがあります。
外用薬
丘疹・膿疱型の酒さにはアゼライン酸外用、イベルメクチンクリーム外用という選択肢もあります。
アゼライン酸は日本では化粧品にも配合されている成分です。15~20%程度のアゼライン酸は、酒さの丘疹や膿疱に対して有効とされます。
イベルメクチンは寄生虫に対する作用や抗炎症作用がある成分で、海外では酒さの治療によく使用されます。
1%のイベルメクチンと0.75%のメトロニダゾールでは、イベルメクチンの方が3週間目から早い改善効果が見られます。
これらは日本では保険適用外です。
イソトレチノイン内服
また重症例では、イソトレチノイン内服(保険適用外)が検討されることもあります。
これは特に丘疹膿疱型酒さに有効とされていますが、催奇形性などの重篤な副作用のため厳密な管理下での使用が必要で、保険診療外となります。
ステロイド外用は酒さを悪化させるため、原則禁忌となります。
自費での治療法
酒さの改善には、こうした保険治療での薬物治療で効果が乏しい場合、特に紅斑毛細血管拡張症(第1度酒さ)はこれらの治療に対する反応が乏しいことが多いです。
そのため、保険適応外となりますが光治療、レーザー治療(Vビームレーザー)が選択肢として上げられます。
当院で行っている酒さの治療
当院では、「これまで治療を行ってきたけど、なかなか改善しなかった」「自分に合う治療法が見つからなかった」という方にも効果を実感していただけるよう、皮膚の状態や症状のタイプに合わせた「保険診療」と「自費診療」による治療を行っています。
保険診療
酒さは、慢性的に再発を繰り返すこともある疾患であるため、当院では継続しやすい保険診療を基本としています。
ロゼックスゲルや抗菌薬の内服は保険適用内で行うことが可能です。これらを症状に応じて処方します。
必要に応じて生活習慣やスキンケア指導も行い、外側と内側の両面から症状の改善を目指します。
ロゼックスゲル外用
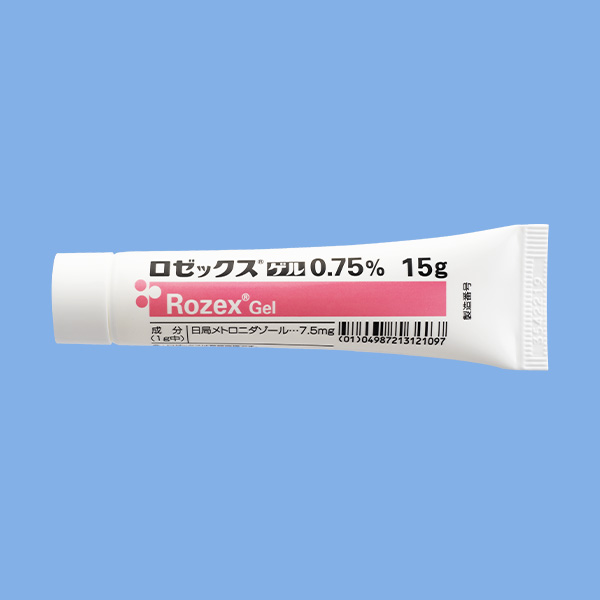
ロゼックスゲルは、酒さ治療に有効なメトロニダゾールを主成分として含む外用薬です。
海外のNational Rosacea Society Expert Committeeのガイドラインでは、メトロニダゾールの外用剤は炎症性丘疹・膿疱型酒さの治療選択肢として推奨されています。
また、日本の「尋常性痤瘡・酒皶治療ガイドライン2023」では、丘疹膿疱型酒さに対して0.75%メトロニダゾールゲルの外用治療を強く推奨(推奨度A)としており、日本における酒さ治療の第一選択薬として位置づけられています。
1日2回、清潔にした患部に塗布して使用します。数ヶ月ほどで症状が改善することが一般的です。
ビブラマイシン/ミノマイシン内服


ビブラマイシンはドキシサイクリン、ミノマイシンはミノサイクリンを有効成分として含む抗菌薬です。主に中等症以上の酒さに対して処方します。
ニキビのような赤いポツポツとした炎症を抑える効果がある内服薬です。2~3ヶ月ほど内服することで治療効果を得られます。
スキンケアのアドバイス
酒さの治療には、スキンケアも欠かせません。当院では、酒さの炎症を悪化させない低刺激で保湿力の高いスキンケアを中心に、洗顔・保湿・紫外線対策までトータルで指導を行っています。
化粧品の選び方や生活習慣の見直しなど、セルフケア面からもアプローチすることで、治療後の再発予防をしたり肌を安定化したりすることが可能です。
自費診療
当院では、より高い効果や再発予防を目指す方向けに、自費診療での酒さ治療も行っています。保険診療で改善が見られなかった方や、赤み・毛細血管拡張・肌の凸凹などの美容面の悩みを同時にケアしたい方に適しています。
ステラM22治療
ステラM22は、IPLを用いた治療です。酒さに伴う毛細血管拡張、肌の色ムラを改善する当院の主力治療です。紅斑性酒さの初期症状に適応されます。
照射した光エネルギーが熱エネルギーに変換され、毛細血管をターゲットに効果を発揮するものです。一度の治療で完了するものというよりは、複数回の施術により徐々に改善していく治療法となります。
イソトレチノイン内服
イソトレチノインは、もともとニキビ治療の内服薬として使われていた薬です。主に、以下のような働きがあります。
- 皮脂腺を小さくする
- 炎症を抑える
- 毛穴を縮小する
これらの働きにより、酒さに対して効果を発揮すると考えられています。イソトレチノインは、酒さの症状のうち、特に丘疹膿疱型と呼ばれるニキビに似た症状が見られるものや、鼻瘤型(肥厚型酒さ)に有効です。
〈女性患者の方へ〉
妊娠中、または妊娠の可能性がある、妊活中の方は絶対に服用できません。
治療中および治療終了後、確実な避妊が必要です。
女性:治療終了後6ヶ月間(厚労省では治療終了後1ヶ月間と記載がございますが当院では最大限リスクを減らすために6ヶ月間としております)
授乳中は服用できません。
〈男性患者の方へ〉
治療中から治療終了後1ヶ月間はパートナーの妊娠を避けてください。
スキンボトックス(マイクロボトックス)
スキンボトックスとは、ボツリヌストキシンを皮膚の真皮層に少量ずつ注射する治療法です。神経性の血管拡張シグナルを抑えることにより、酒さによる赤みを改善する効果の他、皮脂を減らしたり毛穴を引き締めたりする効果も期待できます。
スキンボトックスによる効果は、約3~4ヶ月持続します。
スキンケアのアドバイス
自費診療を受けられる方にも、スキンケアのアドバイスを行っています。酒さでは、肌のバリア機能が低下していると考えられているため、刺激の少ないスキンケアを行うことが重要です。
抗炎症作用や皮脂抑制作用のあるアゼライン酸や、バリア機能を改善したり炎症を抑えたりするナイアシンアミドなどを使ったスキンケアの提案を行っています。
酒さの保険診療と自費診療の選び方
酒さの治療は、症状の程度や目的に応じて保険診療と自費診療を使い分けることが重要です。
当院では、肌の状態を丁寧に診察し、どちらの治療が最適かを一人ひとりに合わせて提案しています。
酒さの治療が初めての方は保険診療
酒さの治療が初めての方は、まず保険診療による基本的な治療をおすすめしています。ロゼックスゲルの外用やビブラマイシン、ミノマイシンの内服は炎症や赤みを抑える標準治療として有効性が確立されているものです。
当院では、初診時に生活習慣やスキンケア習慣も丁寧に確認し、薬物療法とセルフケアを組み合わせて、無理なく続けられる治療プランを提案しています。
保険診療で効果が不十分だった方は自費診療
保険診療で一定の改善が見られても、「赤みが残っている」「再発を繰り返す」「肌質を整えたい」と感じる方には、自費診療を提案することがあります。
ステラM22による光治療は毛細血管の拡張の抑制効果、スキンボトックスは赤みを引き起こす神経性の血管拡張シグナルを抑える効果が期待でき、赤みを根本からケアすることが可能です。
当院では、保険診療で得た経過を踏まえ、より高い満足度を目指すための治療をご案内しています。
酒さのスキンケア・ホームケア
悪化因子の除去やスキンケアも大切です。
悪化因子の除去では、暑かったり寒かったりする生活環境、アルコールや香辛料など刺激の強い食べ物、紫外線、医薬品や化粧品など、生活の中で原因となっているものに関し、それらをなるべく遠ざけるようにします。
またスキンケアでは、保湿や洗顔方法、紫外線対策が重要で、低刺激など化粧品選びも大切です。
具体的には保湿はアゼライン酸が入ったスキンケアを使用しましょう。
酒さはバリア機能が低下し、炎症が病態に関与しているため、セラミド(バリア機能)やグリチルリチン酸2Kなどの(抗炎症成分)を含む低刺激なスキンケアを取り入れましょう。
また紫外線により、酒さの悪化のきっかけとなることがあるためUV対策は欠かせません。
洗顔は肌にできる限り負担をかけないように泡洗顔を選びましょう。
当院では酒さに対するスキンケア指導も行っています。
ぜひご相談ください。
酒さは、長期的な管理が求められる疾患です。
当院では、肌の状態を丁寧に観察しながら、薬による治療のほか、生活環境・習慣やスキンケアに関しても、患者さま一人ひとりに合わせたアドバイスを行っていきます。
酒さは、日常生活や精神的な負担にもつながる疾患です。
当院では、酒さに悩む患者さまに寄り添った丁寧な診療を行っています。
気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。

監修:
新宿駅前IGA皮膚科クリニック 院長 伊賀 那津子
日本皮膚科学会皮膚科専門医・医学博士
京都大学医学部卒業
